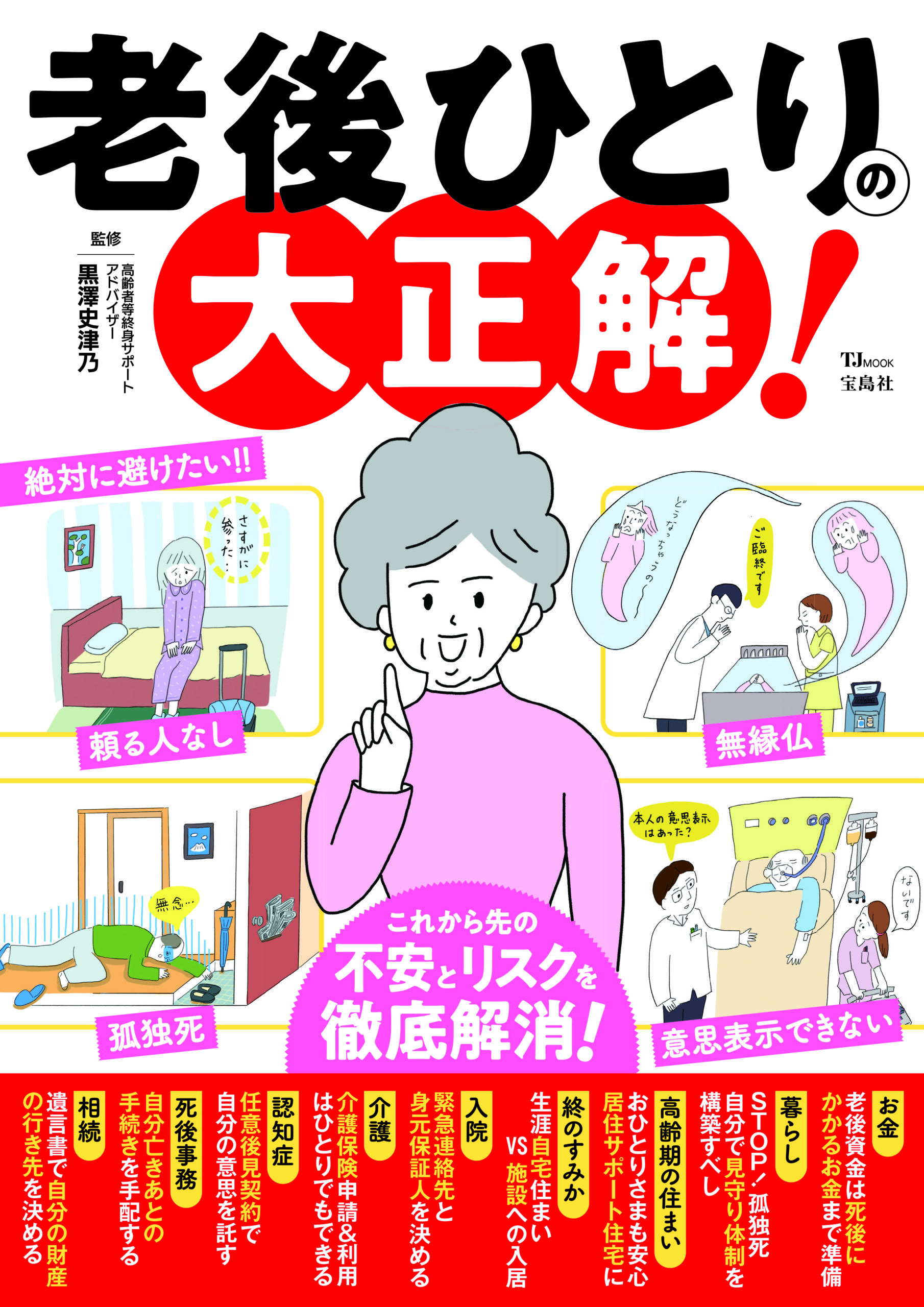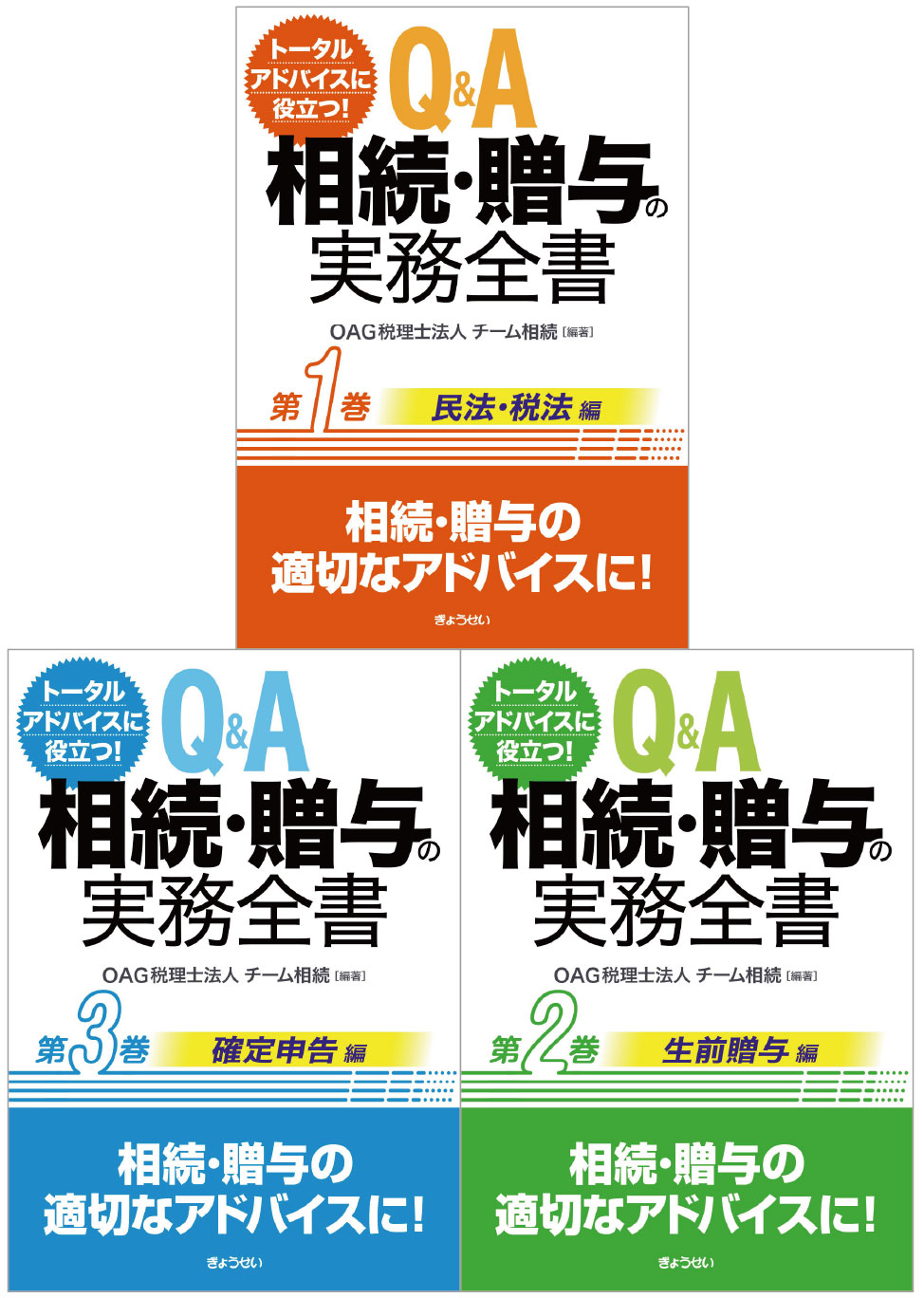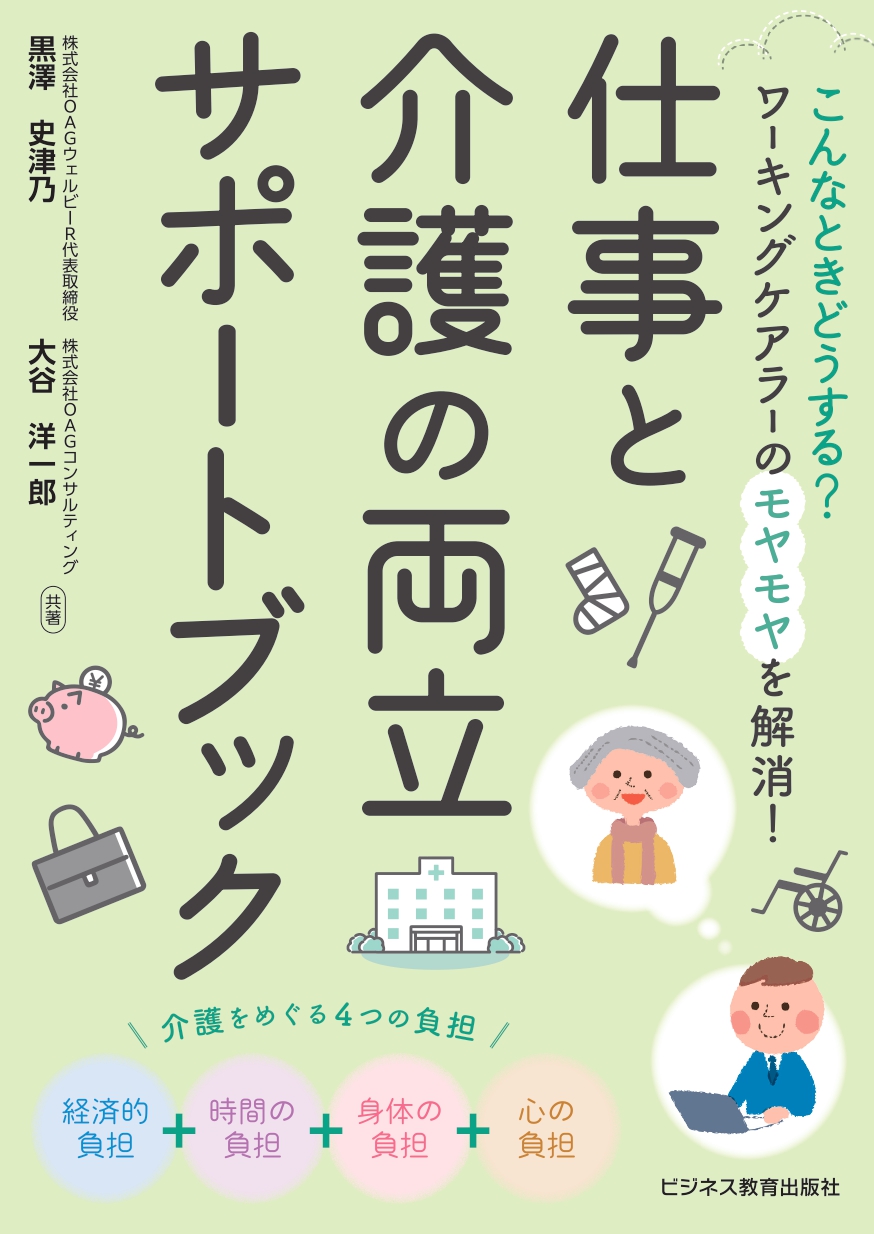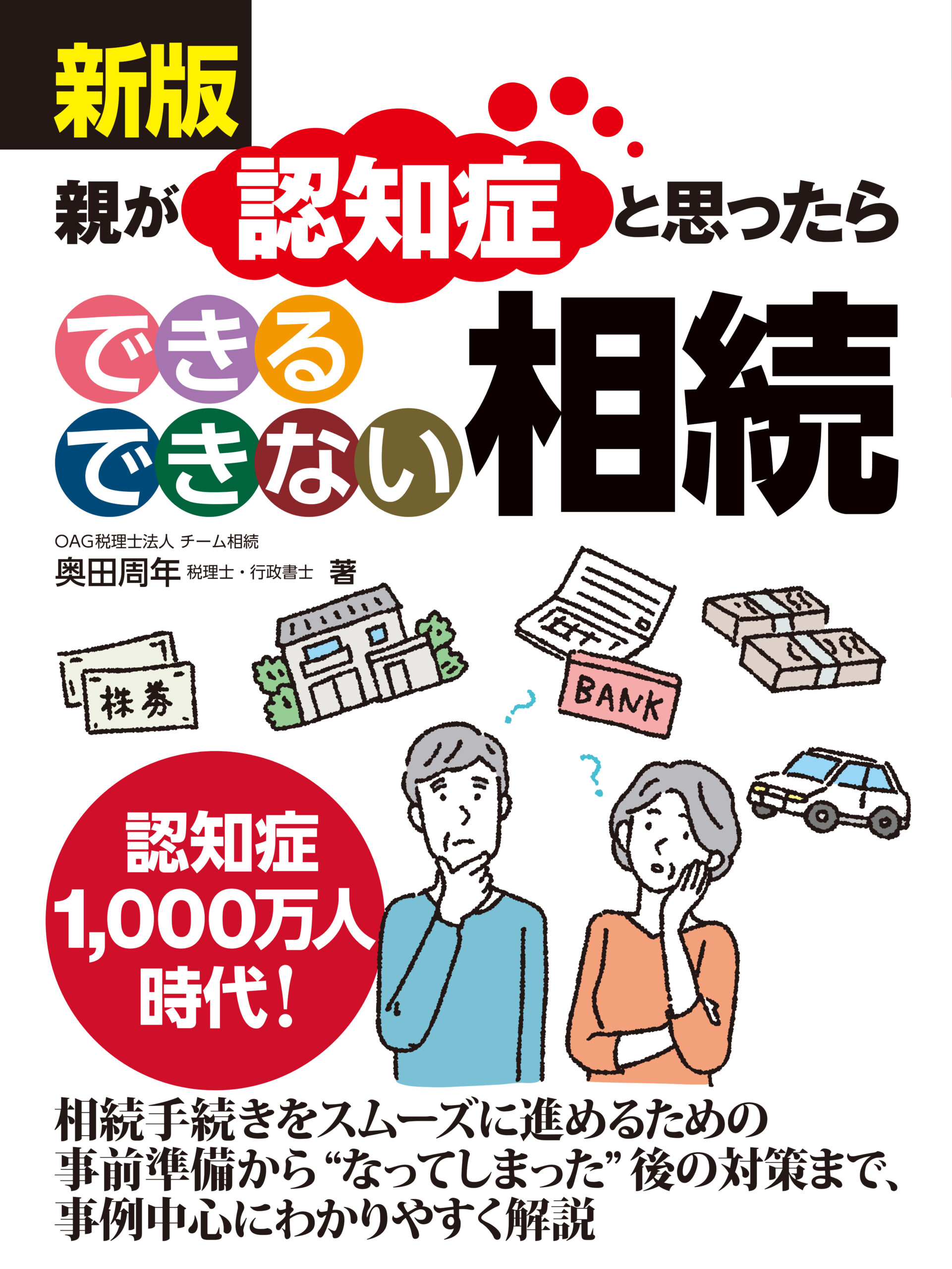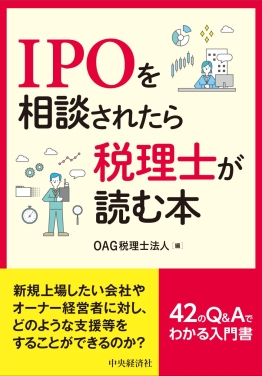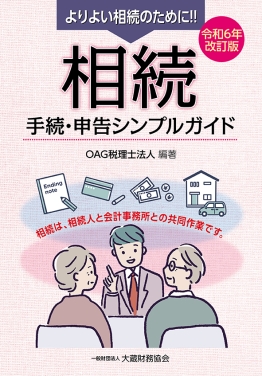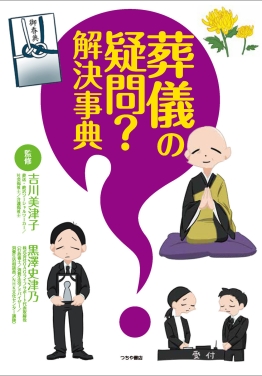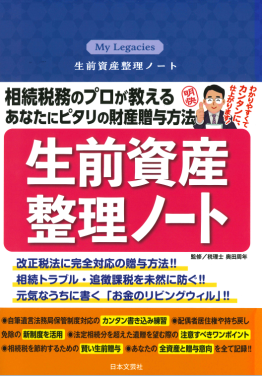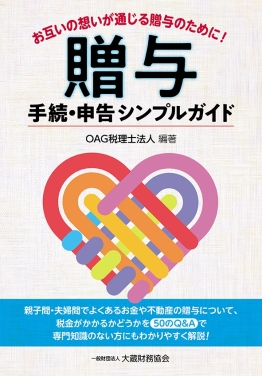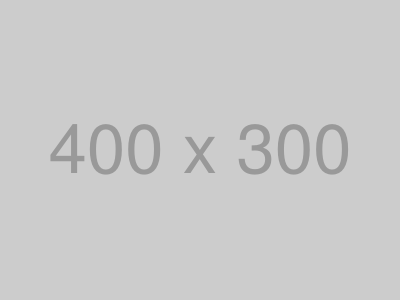
拠点一覧
-
札幌
北海道札幌市中央区北1条西8丁目2-39
ISM札幌大通ビル4階 -
仙台
宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー10階CROSSCOOP内 -
埼玉
埼玉県川越市脇田本町13-5
川越第一生命ビルディング3階 -
東京ウエスト
東京都調布市布田4-6-1
調布丸善ビル3階 -
千葉
千葉県千葉市中央区新町1−17
JPR千葉ビル8F -
幕張本郷
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-3-26
八重寿ビル -
名古屋
愛知県名古屋市中区錦2-13-30
名古屋伏見ビル9階 -
大阪
大阪府吹田市江坂町1-13-33
HF江坂駅前ビルディング7階 -
福岡
福岡県福岡市中央区天神二丁目7番21号
天神プライム12階 -
鹿児島オフィス
鹿児島県鹿児島市武1-2-10
JR鹿児島中央ビル4・5F -
富士吉田【計算センター】
山梨県富士吉田市松山4-3-14
アークフジ1階3号室